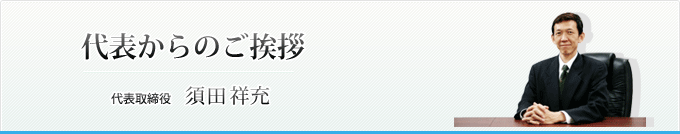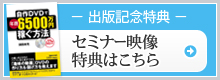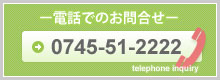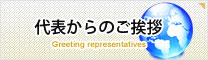ホーム > 代表挨拶
当社はインターネットに軸足を置き、ネットショップの運営から販売企画、提案、各種セミナーの実施、映像コンテンツの製作まで
トータルにインターネットビジネスを支援する新しい企業です。
特にネットショップにおけるインターネットマーケティングを得意とし、これなで多くのセミナーや講座を開いてまいりました。
地元では、奈良県立図書情報館においてネットショップの運営ノウハウを学ぶ「やまとネットショップ成幸塾」を年間を通じて
開講し、塾長を務めています。また、奈良県内各地の商工会議所、学校、各種イベントにて単独セミナーも行っています。
社名のBa・lanza の社名の由来についてご紹介します。
私がインターネットを使ったビジネスを軌道に乗せて、このまま独立をしようか、副業のままにしておこうか
迷っていた時期がありました。
ちょうどその時、ある映画に再会しました。
それは『てんびんの詩』という、実話を元に製作された古い映画です。
社員研修などで上映される機会も多いので、ご存じの方もいらっしゃると思います。
内容は、近江商人の息子である主人公の大作が、小学校卒業と同時に修業に入った鍋蓋の行商
を通じて「商売とは何ぞや」ということを経験的に学んでいく映画です。
大作が行商の修業を開始した当初、彼は自分の理屈で行商をしていました。
なぜならば、行商が成功しない限り、家を継ぐことができなかったからです。
そのために、時にはウソをついたり、相手を騙して鍋蓋を売ろうとしたりしますが、
そんな心構えでは誰も鍋蓋を買ってくれません。
何カ月も売れない日々が続いたある日、ふと農家の洗い場に使い古しの鍋蓋が置いてあるのを目にしました。
これを見つけた大作は「この鍋蓋を盗んでしまえば、困った人が自分の鍋蓋を買ってくれるかもしれない」
という邪な考えを思いつきます。
しかしすぐに、自分と同じように誰かが苦労して売った鍋蓋だと思い直しました。
すると大作は急に愛おしくなり、その鍋蓋を無心に洗い始めました。
その姿を見た鍋蓋の持ち主は、最初は怪訝そうな顔をしたものの、
自分の子と同じぐらいの年齢の大作の気持を聞いて応援したくなり、
鍋蓋をひとつ購入してくれました。
さらに近所の人にも勧めてくれて、鍋蓋は完売したのです。
こうして彼は「売る側と買う側の心がひとつになったとき、はじめて物が売れるのだ」ということに気付きます。
前述したように、私がこの映画を最初に見たのは会社の新人研修でした。
しかし、そのときには何も感じませんでした。
「ふ~ん。昔はこういうことをやっていたのか」
その程度の感想しか持ちませんでした。
ところが、それから20年経ったあるセミナーで「てんびんの詩」の話題が出たのです。
私はもう一度「てんびんの詩」を見てみたくて、あちこちのビデオレンタル店を探しました。
ようやく入手し、かすかな記憶と共にその映画を自宅で見たのですが......すると涙が、涙が止まらないのです。
もう恥ずかしいのも忘れ、声を出して泣いてしまったのです。
会社の新人研修で見たときは、まったく泣けなかったのに、なぜ
20年も経ったときに、涙が止まらないのでしょうか?
それは私がサラリーマン時代、営業で商品を売るためにいろいろな経験をしてきたからなのでしょうか。
「商売とは何か?」
「ものを売ることとは何か?」
「ものを買うこととは何か?」
「商売人とはどうあるべきか?」
そして「人間とは?」
そうした商売に関するすべての原点を教えられ、私の心の深い部分にも突き刺さる思いがしました。
それ以来、私は自分のビジネスが行き詰まったときには、必ずこの『てんびんの詩』を見て原点
に戻ることにしています。恥ずかしいのですが、もちろん今でも見るたびに泣いてしまいます。
その商売の原点を忘れないようにしようと、私はこの映画のタイトル『てんびんの詩』を自分の
会社の社名にしようと考えました。それがBa lanza (バランサ)です。
この言葉はスペイン語で「てんびん」「てんびん座」を意味します。
この社名への思い、初心を忘れず、これからも自分のビジネスを成長させていきたいと思います。
![]()